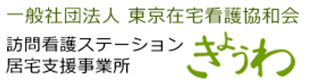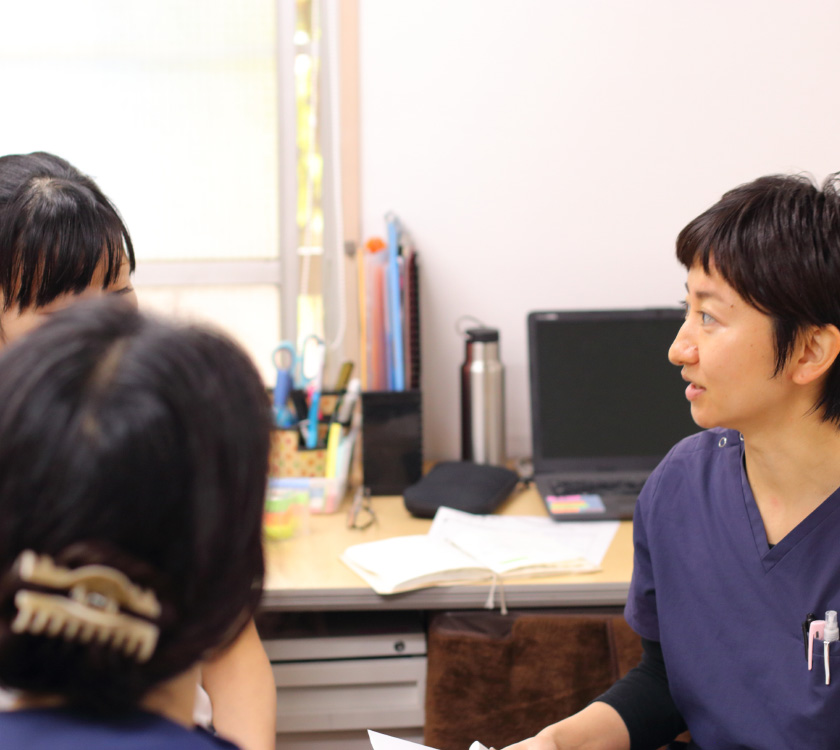NEWS協和会ニュース
-
2023.11.20お知らせ
年末年始の営業について
ご契約時にお伝えしております通り、年末年始(12月29日~1月3日)は休業ですが、緊急連絡対応は可能です。
また、点滴や処置など、お休みの間もケアが必要な方には当番の看護師が訪問致しますので、担当看護師とご相談ください。
-
2023.11.20お知らせ
11月30日(木) 9:00~ 第59回 きょうわ会 地域交流セミナーを行います。
今回は「安心してお家で過ごそう!~人工呼吸器装着編」というテーマでやよい訪問看護ステーション管理者 野呂美香氏に講義をして頂きます。
看護職、介護職、ケアマネジャー皆様お誘いあわせの上、ご参加お待ちしております。
-
2023.08.02協和会ニュース
協和会ニュース79号(2023年8月2日発行)を発行いたしました
-
2023.05.01協和会ニュース
協和会ニュース77号(2023年5月1日発行)を発行いたしました
-
2023.08.02協和会ニュース
協和会ニュース79号(2023年8月2日発行)を発行いたしました
-
2023.05.01協和会ニュース
協和会ニュース77号(2023年5月1日発行)を発行いたしました
-
2023.01.25協和会ニュース
協和会ニュース76号(2023年1月25日発行)を発行いたしました
-
2022.11.01協和会ニュース
協和会ニュース75号(2022年11月1日発行)を発行いたしました。
-
2023.11.20お知らせ
年末年始の営業について
ご契約時にお伝えしております通り、年末年始(12月29日~1月3日)は休業ですが、緊急連絡対応は可能です。
また、点滴や処置など、お休みの間もケアが必要な方には当番の看護師が訪問致しますので、担当看護師とご相談ください。
-
2023.11.20お知らせ
11月30日(木) 9:00~ 第59回 きょうわ会 地域交流セミナーを行います。
今回は「安心してお家で過ごそう!~人工呼吸器装着編」というテーマでやよい訪問看護ステーション管理者 野呂美香氏に講義をして頂きます。
看護職、介護職、ケアマネジャー皆様お誘いあわせの上、ご参加お待ちしております。